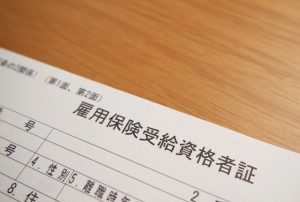新着情報
就業規則の周知と義務とは?
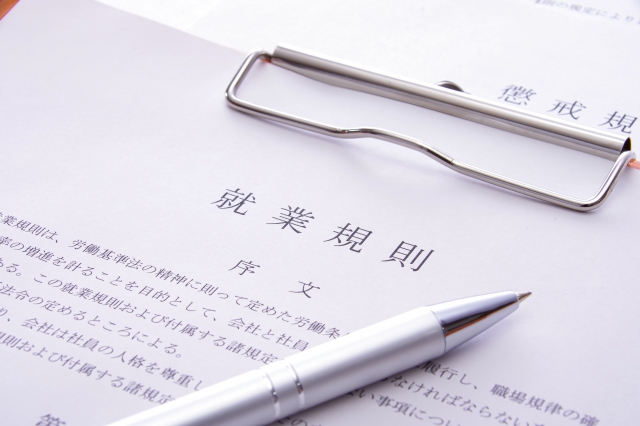
企業が従業員を雇用する際、労働条件を明確にするために必要となるのが「就業規則」です。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する企業に対し、就業規則の作成・届出義務とともに、その周知を義務付けています。
本記事では、就業規則の周知方法や範囲、不利益変更時の対応について解説します。
就業規則の周知の方法は?
就業規則の周知方法として、労働基準法施行規則第52条の2に基づき、以下のいずれかの方法が求められます。
書面の交付
従業員一人ひとりに紙媒体で配布する。
社内掲示・備え付け
事業所内の見やすい場所に掲示、またはファイル等で管理し、従業員が自由に閲覧できる状態にする。
電子データでの提供
社内ネットワークやイントラネット、クラウドストレージ上にアップロードし、全従業員がアクセス可能にする。
このように、従業員が容易に就業規則を確認できる状態を整えることが重要です。
就業規則の周知のタイミングは?いつ行うの?
就業規則の周知は、以下のタイミングで行うのが望ましいとされています。
新入社員の入社時
オリエンテーションや研修時に説明し、書面やデータで提供する。
改訂時
就業規則を変更した際には、変更点を明確にし、従業員に通知する。
定期的なリマインド
従業員に改めて周知する機会を設ける(例:年1回の確認会)。
これにより、従業員が常に最新の就業規則を認識し、適切な行動を取れるようになります。
就業規則を周知しなければならない範囲はどこまで?内規の周知は必要?
就業規則は、すべての従業員に周知する義務があります。
正社員、契約社員、パート・アルバイトも対象
労働契約の形態に関わらず、全員が周知対象。
内規(細則・ガイドライン)についても周知推奨
必ずしも法的義務ではありませんが、トラブル防止の観点から、内規も適切に周知することが望ましい。
就業規則の周知は10名未満の場合には必要?
労働基準法上、常時10人未満の事業所には就業規則の作成義務はありません。
しかし、就業規則の作成・周知はトラブル回避のために推奨されます。
労働条件の明確化
労使間の認識違いを防ぐ。
労働紛争の予防
ルールを明確にしておくことで、後のトラブルを回避。
従業員の安心感向上
働く上でのルールが明確になり、労働環境の向上につながる。
就業規則の周知に関わる判例

就業規則の周知義務に関する重要な判例として、「フジ興産事件(最高裁判決平成15年10月10日)」があります。
この判例では、就業規則が適用されるためには、従業員に対し周知されていることが条件であると判断されました。
このように、周知が不十分な場合、就業規則の内容が無効とされる可能性もあります。
不利益変更の際の周知の方法
就業規則の変更が労働者にとって不利益となる場合、適切な手続きを踏む必要があります。
変更理由の説明
なぜ変更するのかを具体的に説明。
労働者の意見聴取
労働組合や従業員代表と協議する。
変更の合理性確保
変更内容が社会通念上、合理的であることを担保。
周知の実施
改訂後の就業規則を明確にし、従業員に伝達。
これにより、従業員の納得感を高め、不満や訴訟リスクを軽減できます。
まとめ
就業規則の周知は、企業のコンプライアンスを守る上で重要な要素です。
- 周知方法:書面、掲示、電子データなどを活用。
- 周知タイミング:入社時、改訂時、定期的なリマインド。
- 周知範囲:正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトにも適用。
- 10名未満でも作成・周知推奨:労働環境の明確化とトラブル防止のため。
- 不利益変更時の対応:合理性を確保し、適切に説明・周知。
適切な周知を行うことで、企業と従業員の双方にとって健全な労働環境を維持することができます。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所