新着情報
【完全解説】休職とは?種類・手続き・社会保険・給与のポイントをわかりやすく解説
2025.04.16
スタッフブログ

そもそも休職とは?欠勤との違い
休職とは、労働者が一定期間、会社との雇用関係を維持したまま労務を免除される制度です。
一般的に、就業規則に基づいて適用されるもので、会社が休職を認めるかどうかの判断を行います。
【欠勤との違い】
| 項目 | 休職 | 欠勤 |
| 期間 | 長期間(数か月~年単位) | 短期間(数日~数週間) |
| 雇用関係 | 維持されるが、復職できない場合は、退職の可能性あり | 雇用関係は基本的に維持 |
| 給与 | 原則無給(休職手当が出るケースもあり) | 欠勤控除により、給与が減額される |
| 理由 | 傷病・事故・自己都合・公職就任など | 突発的な事情による休み |
休職の種類
休職には複数の種類があり、主に以下のように分類されます。
傷病休職
病気やケガで働けない場合に適用される休職です。
【ポイント】
- 医師の診断書が必要
- 休職期間満了後、復職不可の場合は退職や解雇の可能性あり
- 健康保険の「傷病手当金」を申請できる(支給条件あり)
事故欠勤休職
業務外の事故などで長期間の欠勤が必要になった場合に適用されます。
【ポイント】
- 交通事故や私的なケガが対象
- 労災保険の対象にならない(業務中の事故は労災の適用)
- 会社の規定により適用の可否が異なる
自己都合休職
自己の事情により休職するケースです。
【ポイント】
- 例:留学・家族の介護・育児など
- 会社の許可が必要
- 無給が基本だが、育児休業給付金などの対象になるケースも
出向休職
グループ会社や他社への出向に伴う休職です。
【ポイント】
- 出向元での雇用関係は維持されるが、給与の支払いは出向先に依存
- 出向期間終了後は復職可能
組合専従休職
労働組合の専従職員(フルタイム活動者)になる際の休職です。
【ポイント】
- 労働組合活動のために勤務を休む
- 給与は会社から支払われず、組合から支給されるケースが多い
公職就任休職
公職(国会議員・地方議員など)に就任した際の休職です。
【ポイント】
- 公職在任中は休職となり、退任後は復職可能
- 一定の要件を満たす場合、会社が復職を拒否することもあり
起訴休職
刑事事件で起訴された社員に適用される休職です。
【ポイント】
- 会社の就業規則により休職の可否が異なる
- 有罪確定で懲戒解雇の可能性がある
社員が休職する際の手続き
休職する場合、基本的な流れは以下の通りです。
- 休職願の提出
会社の人事部や上司に相談
休職理由・期間を明記し、必要書類(診断書など)を添付 - 会社の承認
就業規則や社内制度に基づき、休職の可否を判断 - 休職開始
会社からの指示に従い、休職手続きを完了
休職中の所得補填「休職手当」
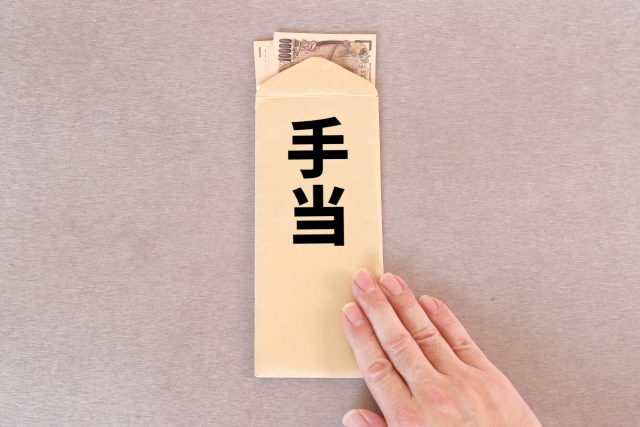
休職期間中は原則として無給ですが、一部のケースでは所得補填の制度が利用できます。
【主な手当制度】
| 制度名 | 支給条件 | 支給額 |
| 傷病手当金 | 連続3日以上の病気・ケガで働けない | 給与の2/3(最大1年6か月) |
| 失業手当(特定理由離職者) | 休職満了後に復職 | 退職前の給与の50~80% |
| 育児休業給付金 | 1歳未満の子を養育 | 休業開始前賃金の67%(半年後50%) |
休職期間中の社会保険料
休職中でも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務は基本的に維持されます。
【支払い方法の例】
- 会社が立て替え → 復職後に精算
- 社員が自己負担(銀行振込など)
- 免除申請(傷病手当金の受給など特定条件下)
退職して社会保険の資格を喪失する場合
休職満了後に退職した場合、社会保険の資格喪失となり、次の手続きが必要になります。
【退職後の選択肢】
- 国民健康保険へ加入
市区町村の役所で手続きが必要 - 健康保険の任意継続
退職後2年間、継続可能(ただし保険料は全額自己負担) - 扶養に入る
配偶者や親の健康保険に加入可能(収入要件あり)
まとめ
- 休職とは:雇用関係を維持したまま長期間労務を免除される制度
- 休職の種類:傷病、事故、自己都合、出向、組合専従、公職就任、起訴など多様
- 手続き:会社への申請が必要(診断書や休職願の提出)
- 給与補填:傷病手当金や育児休業給付金などの制度あり
- 社会保険:休職中でも継続加入が原則、退職後は別途手続きが必要
休職制度を理解し、適切な対応を取ることで、従業員と企業双方にとって最適な選択ができます。
大阪なんば駅徒歩1分
給与計算からIPO・M&Aに向けた労務監査まで
【全国対応】社会保険労務士法人 渡辺事務所



